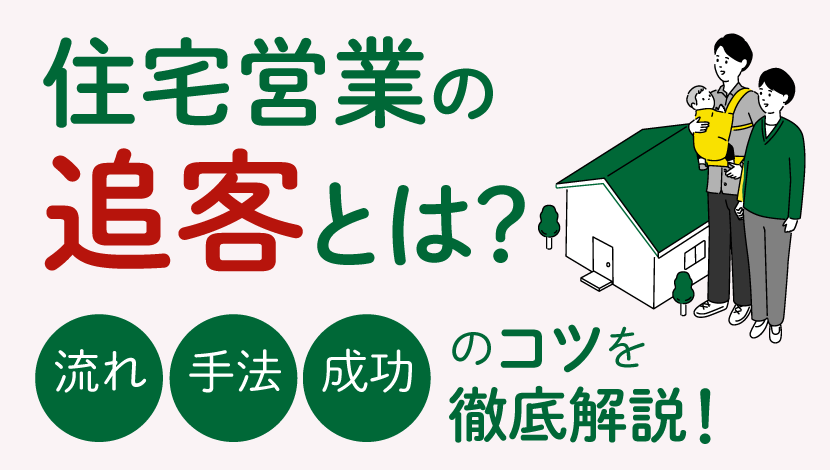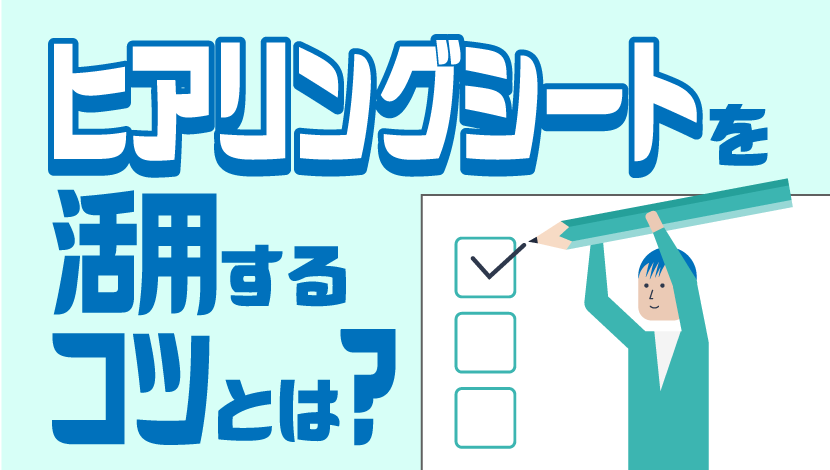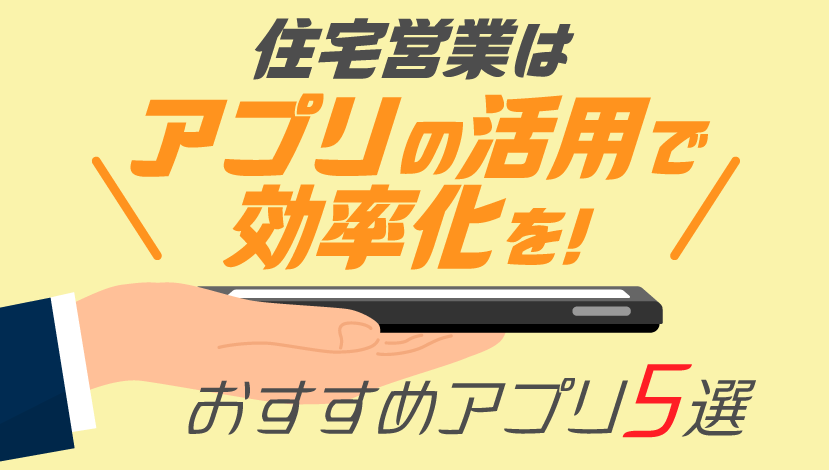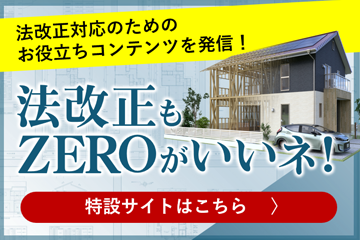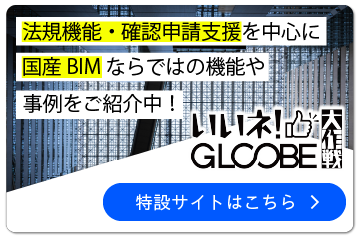住宅営業における追客とは

住宅営業における追客とは、一度接点を持った見込み客に対して、継続的にアプローチを行い、信頼関係を構築する方法です。
住宅という高額かつ検討期間の長い商材においては、初回接客だけで成約に至ることはまれであり、複数回にわたる接点を通じて、顧客の購買意欲や期待を徐々に高めていく必要があります。
追客の目的は、接触回数を増やすことではありません。重要なのは、顧客にとって価値ある情報をタイミングよく届け、顧客から「この会社になら任せられる」と感じてもらうことです。
そのためには、営業担当者の直感や経験だけに頼るのではなく、顧客の関心度や過去の反応データを踏まえた戦略的なアプローチが求められます。
たとえば、展示場への来場後にすぐにお礼メールを送り、数日後に役立つ住宅情報を提供。数週間後には資金計画に関する資料を送付するといったように、段階的にコミュニケーションを深めていくことが理想です。
そうすることで、顧客の心理的ハードルを下げ、商談やクロージングへと自然につなげられます。追客は、営業の後半戦を制するための鍵となるプロセスです。適切に実行できれば、営業成績の安定化やリード獲得のROI改善などのメリットにも直結します。

なぜ住宅営業で追客が重要なのか

住宅営業において追客が重要とされる理由は、住宅という商材の特性にあります。
住宅は数千万円単位の高額商品であり、ほとんどの顧客にとっては一生に一度の大きな買い物です。そのため、購入までにかかる検討期間が長く、一度の接触だけで即決に至ることはほとんどありません。
たとえば、展示場に来場した時点では情報収集のつもりだった顧客が、数ヶ月後に本格的に購入を検討し始めるケースは多々あります。このような顧客に対して、接点を持ち続けられるかどうかが、その後の成約に大きく影響します。
また、住宅検討者は複数社を比較するのが当たり前だからこそ、追客で最後まで検討リストに残ることが重要です。どれだけ良い商品サービスを持っていても、接点が薄れてしまえば候補から外されてしまう可能性は高くなります。
検討が長期化する中で定期的なフォローを受けた顧客は、「この会社は自分たちに関心を持ってくれている」と感じやすくなり、競合他社との差別化にもつながるでしょう。
住宅営業における追客の流れ

住宅営業における追客は、単発的なアプローチではなく、段階を踏んで顧客の検討状況に寄り添いながら進めていく必要があります。
初期接触から商談・契約に至るまでのプロセスのなかで、タイミングや手法を適切に使い分けることで、成約率の向上につながります。ここでは、一般的な追客の流れを4つのフェーズに分けて解説します。
初期接触(展示場・問い合わせ後の対応)
追客の出発点は、展示場への来場やWebからの資料請求・問い合わせなど、見込み客との最初の接触です。
この段階では、顧客の関心が最も高まっているため、スピーディーな対応が欠かせません。たとえば、来場当日中にお礼メールを送ったり、問い合わせから24時間以内に電話でフォローしたりするなど、即時対応によって信頼感を与えます。
また、初期接触では顧客の基本的な情報(家族構成・予算感・希望エリアなど)を収集し、後の追客に活かすための土台を築くことが大切です。
初回対応の質が低いと、その後の追客の効果にも大きく影響するため、ここは営業プロセス全体の成否を分ける重要なポイントです。
▼住宅営業における「見込み客」については、ぜひこちらの記事もご覧ください。
住宅営業の見込み客とは? 集客方法から成功ポイントまで解説|FCA JOURNAL|建築CAD - 福井コンピュータアーキテクト
情報提供・信頼構築の段階
初回接触後すぐに商談へと進むケースは稀です。多くの場合、検討を進める中で他社と比較したり、家族と相談したりする期間が生まれます。この期間こそ、追客による情報提供と信頼構築のチャンスです。
具体的には、顧客の興味に応じて以下のような関連情報を、LINEやメルマガを通して段階的に届けるようにしましょう。
-
家づくりの基本ガイド(注文住宅と建売住宅の違いなど)
-
資金計画の考え方や住宅ローンに関する解説
-
間取り事例や実際の施工写真、入居者の声
これらの情報提供を通じて、営業担当者への信頼感や安心感が高まり、商談につながる確率が上がります。また、やり取りのなかで少しずつニーズを深掘りすることで、より精度の高い提案準備も可能になります。

見込み度合いに応じた接触頻度の調整
すべての見込み客に同じ頻度・内容でアプローチしていては、営業リソースが不足してしまいます。そこで重要になるのが、顧客の見込み度合い(温度感)に応じた対応の最適化です。
温度感の分類例は以下の通りです。
-
Hot:購入意思あり。積極的に資料請求や来場
-
Warm:情報収集中だが具体的検討はこれから
-
Cold:興味はあるが時期未定、情報収集レベル
この温度感を見極める指標として、LINEの既読率、メール開封率、Webページの閲覧履歴、問い合わせ内容などが活用されます。たとえば、特定の資料を3回以上閲覧している顧客やイベント案内への反応が早い顧客は、Hot層と判断できる可能性があります。
Hot層には電話や個別訪問を、Warm層には定期的な情報提供を、Cold層にはリターゲティング広告やDMでの接点維持を図るなど、段階に応じてアプローチを変えることが追客の効率化につながります。
商談・クロージングへの移行
継続的な追客によって信頼関係が深まると、いよいよ商談・クロージングの段階へ進みます。このタイミングでは、顧客に寄り添った提案と不安の払拭がポイントになります。
提案にあたっては、これまでのやり取りを踏まえた「自分たちのために考えられたプラン」だと感じてもらえることが重要です。過去のコミュニケーション歴をもとに、個別化したプランを作成しましょう。
また、資金計画やローン審査、引き渡しスケジュールなど、実務的な確認も行いながら、最終的な判断を後押しします。この段階でのミスや対応の遅れは、信頼を損なうリスクがあるため、関係者との連携や社内体制の整備も欠かせません。
クロージングとは、追客の集大成であり、最終ゴールではなく、その後のアフターフォローにもつながるスタート地点でもあります。
住宅営業における主な追客手法

追客を成功させるには、顧客の検討状況や心理に合わせて、複数の手法を使い分けることが大切です。営業担当者が手動で連絡を取るだけでなく、ツールやデジタルチャネルを組み合わせて、効率的かつ効果的に接点を持続させる仕組みが求められます。
ここでは、住宅営業において代表的な追客手法を紹介します。
メール
メールは、最も基本的な追客手法のひとつです。来場のお礼やイベント案内、最新物件情報などを定期的に送ることで、接点を継続できます。メールは比較的長文で情報を伝えられるため、詳細な資料や施工事例の紹介にも適しています。
一方で、開封率やクリック率を定期的に確認し、効果が薄れている場合はコンテンツの改善や頻度調整が必要です。開封率が一定以上の顧客は、購買意欲が高まっているサインと見なせます。
LINE
LINEは即時性が高く、日常的に使われているため、顧客の心理的ハードルが低く、反応率も高めです。メッセージ形式が短くカジュアルなので、リマインドやライトなコンテンツ配信に適しています。
たとえば、モデルハウスの空き状況の案内や資金相談会の予約受付などを気軽に届けられます。また、開封・既読・URLクリックなどの行動データを蓄積すれば、顧客の温度感を定量的に把握する材料にもなります。
SNS
InstagramやFacebookなどのSNSは、ブランディングや間接的な追客に効果を発揮します。施工事例や完成写真、入居者インタビューなどの投稿を通じて、住宅会社の世界観や施工品質を訴求することが可能です。
SNSは情報の受動的な発信だけでなく、コメントやDMなどを通じた個別接点の起点にもなります。とくにInstagramのストーリーズやリールを活用することで、タイムリーな訴求や感情的な共感を引き出しやすくなります。
リターゲティング広告
一度接触したものの、しばらく行動のないColdリードに対しては、リターゲティング広告が有効です。自社サイトを訪問した顧客に対し、SNSやWeb広告で再度アプローチをかけ、自社を思い出してもらう効果があります。
広告の内容は、検討ステージに合わせて調整します。たとえば、再来場を促すキャンペーン告知や来場特典の案内など、行動を促すメッセージ設計が効果的です。広告経由で再来場した顧客は、興味関心が高まっている可能性があり、商談化につながりやすくなります。

電話
電話は、温度感の高い顧客や提案フェーズに移行した顧客へのアプローチに適しています。直接話せることで、顧客の不安や疑問をその場で解消でき、提案への移行もスムーズに進みます。
一方で、Cold層に対して無理に電話をかけると、かえって悪印象につながるリスクもあります。過去の接触履歴や行動データをもとに、連絡すべき相手とタイミングを見極めることが肝心です。
DM
DM(ダイレクトメール)は、Webにあまり反応しない層や紙媒体を好む顧客へのアプローチに有効です。施工事例の冊子や資金計画ガイド、限定イベントの招待状など、コンテンツに工夫を凝らすことで、温度感を高められます。
印刷・送付にコストはかかりますが、手元に残る媒体としての存在感はデジタル以上です。とくに、個別対応が難しいCold層への追客において、印象を残す手段として活用する価値があります。
住宅営業における追客体制の構成要素

追客は営業担当者の努力だけで継続・最適化できるものではありません。組織としての体制が整っていなければ、せっかくの見込み客を機会損失してしまう恐れがあります。
属人化を防ぎ、効率よく成果につなげるためには、情報管理・業務分担・ツール活用といった体制整備が不可欠です。ここでは、住宅営業における追客体制の中核をなす3つの要素を解説します。
CRM・SFAの活用
追客を属人化させずに仕組み化するために欠かせないのが、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)の活用です。これらのツールを導入することで、顧客情報を一元管理し、接触履歴や対応履歴、顧客の温度感などを可視化できます。
たとえば、LINEでのやり取り履歴や資料送付のタイミング、Webからの資料ダウンロードなどの行動データを時系列で確認できれば、次にどのようなアプローチをすべきかの判断が容易になります。
また、他の営業担当への引き継ぎもスムーズになり、チーム全体での顧客対応の質が底上げされます。
営業チーム内での役割分担
住宅営業の現場では、1人の営業担当が新規接客から追客、契約対応までを一手に担っているケースが多く、追客にまで十分な時間を割けないという課題が生まれがちです。こうした状況を防ぐには、営業チーム内での役割分担が効果的です。
たとえば、新規来場者への対応をメインとする担当と既存リードの追客を専門とする担当を分ける体制を取れば、フォローが後回しになるリスクを減らせます。また、誰が、どの顧客をフォローしているかを明確にしておくことで、二重対応や対応漏れの防止にもつながります。
営業DXの推進
住宅業界では、申込書やプラン図面、契約書類などの紙業務が依然として多く、営業担当が膨大なペーパーワークに追われている現場も少なくありません。事務作業に時間を奪われることで、追客に十分なリソースを割けないという構造的な課題が存在しています。
だからこそ、営業DXの推進が必要です。電子契約や顧客対応の自動記録、営業進捗の可視化などを実現する専用SFAツールを導入すれば、事務負担の軽減だけでなく、営業ノウハウの共有や属人化の解消にもつながります。
住宅業界向けの営業支援アプリ「iPlanView」では、顧客情報や進捗状況を一元化し、営業チーム内で共有・運用できる仕組みが整っています。こうしたツールの活用が、追客体制の強化に直結するのです。
▼住宅営業に活用できるアプリについては、ぜひこちらの記事もご覧ください。
住宅営業はアプリの活用で効率化を! 導入にあたっての選び方解説やおすすめアプリ5選も紹介|FCA JOURNAL|建築CAD - 福井コンピュータアーキテクト
住宅営業の追客を成功させるポイント

追客を成果につなげるには、顧客の心理や行動、情報接触のチャネルごとの特性を理解し、それに応じたアプローチの設計が欠かせません。また、データに基づく判断や、ITツールを活用した効率化も重要です。
ここでは、住宅営業の追客を成功に導くための3つのポイントを解説します。
顧客心理に合わせたタイミングの見極め
追客で最も重要なのは、購買意欲が高まるタイミングを見極めることです。
営業担当者が焦って早すぎる提案をしてしまえば、顧客に「まだ検討段階なのに…」と引かれてしまう可能性があります。逆に、絶好のタイミングを逃せば、他社に流れてしまうリスクもあるのです。
そこで活用したいのが、行動データです。
LINEのメッセージを3通連続で既読、資料のダウンロード、Webサイトの特定ページを複数回閲覧などは、顧客の関心が高まっているサインです。こうしたシグナルをもとに、最適なタイミングで提案につなげることで、商談化の確率が格段に上がります。

チャネル・段階別にコンテンツを設計する
追客の効果を最大化するには、使うチャネルと届けるコンテンツの最適化が欠かせません。同じ内容でもLINEとメール、電話では伝わり方が異なり、リードの温度感や検討段階によって、受け取る側の反応も大きく変わります。
具体的には以下のような使い分けが有効です。
-
メルマガ:幅広い情報を網羅的に配信(例:施工事例・イベント情報)
-
LINE:簡潔なリマインドや反応促進(例:来場予約、限定資料の案内)
-
電話:温度感の高い顧客への個別提案やヒアリング
-
DM:Coldリードに印象を残す紙媒体
また、ファネルの上部(情報収集層)には住宅の基礎知識や費用感の紹介、中間層には他社との違いを伝える比較資料、ファネル下部には契約事例や保証内容など、検討段階に応じたコンテンツ設計が重要です。
ITツールの導入を検討する
追客を個人の経験と記憶に頼っていると、情報の抜け漏れや対応の遅れが起こりやすくなります。特に、Excelなどで顧客管理を行っている現場では、「記録し忘れ」「誰が対応しているかわからない」といった属人化の課題が頻出します。
そこで有効なのが、ITツールによる一元管理と可視化です。
CRMやSFAを導入すれば、顧客のステータスや過去の対応履歴、関心度に応じたアプローチ内容をチーム全体で共有できます。営業活動が可視化されることで、個人のスキル差に左右されない安定した追客体制が築けます。
▼住宅営業に活用できるさまざまなツールについては、ぜひこちらの記事もご覧ください。
住宅営業の支援ツールに注目! ポイント解説やおすすめのツールを紹介|FCA JOURNAL|建築CAD - 福井コンピュータアーキテクト
住宅営業における追客を仕組み化して成果につなげよう
住宅営業における追客は、個々の営業担当の努力だけでは成果を安定させにくい領域です。
重要なのは、属人化に頼らず、組織全体で再現性のある仕組みを構築すること。顧客情報の一元管理、チャネル別のコンテンツ設計、データにもとづくタイミング判断などを標準化することで、誰が対応しても一定の成果を出せる体制が整います。
近年では、デジタルツールの活用によって追客の質と効率を高める企業が増えています。顧客データや行動履歴を自動で蓄積・可視化し、適切なタイミングで情報発信や提案を行うことで、信頼構築からクロージングまでの流れをスムーズにできます。
住宅セールスプラットフォーム「iPlanView」は、顧客情報の一元管理とデジタル接客を両立できるシステムです。
iPadを使ってお客様の理想の暮らしをヒアリングし、土地条件や法規制を自動でチェック。3D・ARによるリアルなプラン提案も可能です。商談内容はクラウドで即共有され、追客の進捗や対応履歴をチーム全体で可視化できます。
属人化しがちな追客業務を仕組み化し、誰でも成果を再現できる環境を整えたい企業にこそおすすめです。