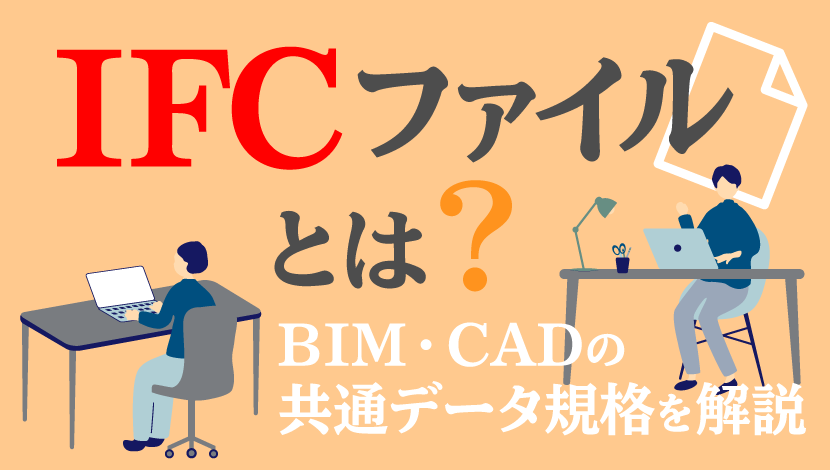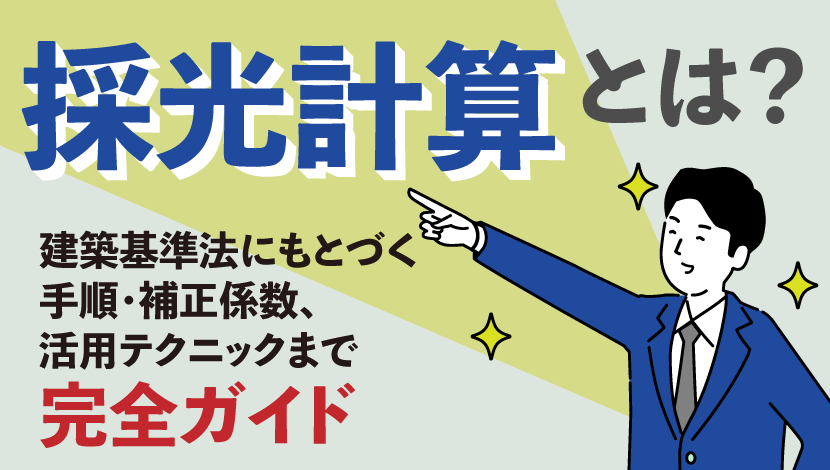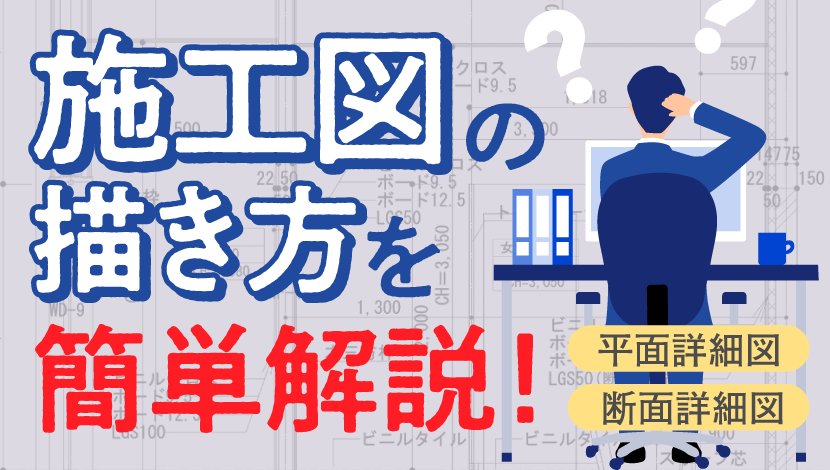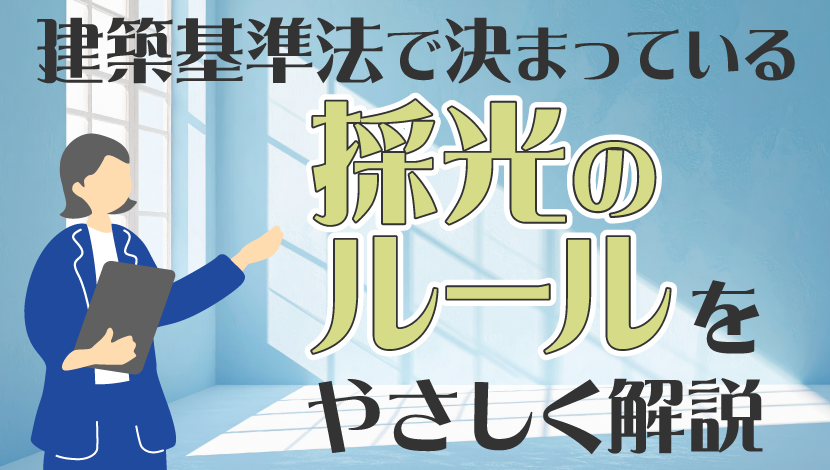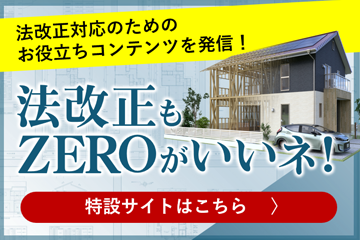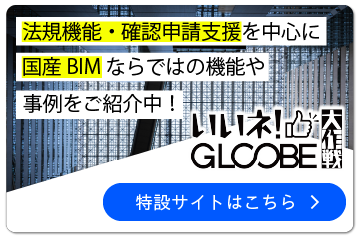IFCファイルとは?
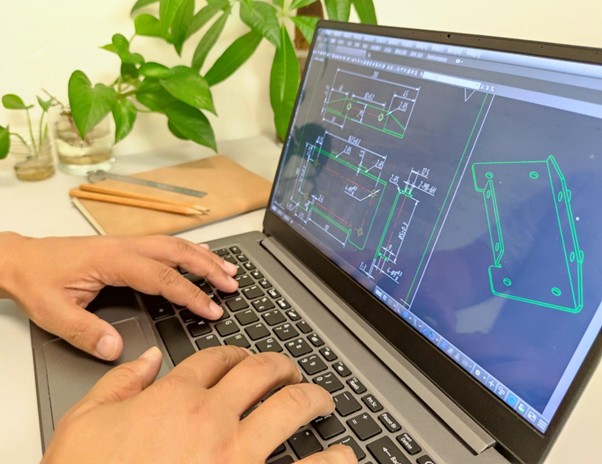
IFC(Industry Foundation Classes)とは建築・建設業界におけるBIM図面の出力データの国際規格(ISO 16739:2013)です。建築現場やプロジェクトでは、さまざまなソフトで作成したデータをやり取りする必要があり、IFCは共通のデータ形式として役立つのです。まずは、IFCの基本的な知識と、どのような情報が含まれているのかをわかりやすく解説します。
IFCとは拡張子のひとつ
IFCは拡張子のひとつ。BIM(Building Information Modeling)データをやりとりするためのファイル形式です。BIMソフトは建築・構造・設備・施工など、建築業界のさまざまな職種で使われます。IFCファイルであれば、柱や壁など建物を構成する要素を、BIMソフトを問わずにやりとりできるのです。
BIMソフトは多岐にわたるため、プロジェクトを進めるうえでデータのやりとりが煩雑になりがちです。しかし、IFCファイルに書き出すことで、作成したBIMソフトに依存せず開いて見ることができます。これによりプロジェクトをスムーズに進めることが可能です。
IFCファイルに含まれるデータ
IFCファイルには、以下のような情報が含まれます。
|
項目 |
内容 |
|
建物の形状 |
壁、柱、スラブ、屋根、窓、ドアなどの3Dモデル |
|
寸法・材質データ |
高さ、幅、厚み、材質、仕上げの種類など |
|
属性情報 |
構造体や仕上げ、用途、性能など |
|
空間・階層構造 |
居室や空間といった用途別の分類など |
|
開口部の情報 |
ドアや窓の位置、サイズ、開き方など |
上記のようにさまざまな情報が含まれていますが、一方で紙の図面でみられるような寸法の表示などの、いわゆる「見せるための表現」までは含まれていないことがあります。プレゼン資料や建築確認などの提出書類を作成するときは、BIMソフトで調整しなければなりません。
IFCファイルの活用方法
IFCファイルは、おもに建築プロジェクトに関わる設計や構造、設備といった複数の担当部門およびそれぞれの担当者が共通認識をもつために使われます。3Dモデルに含まれる情報を同じ形式で持つことができるため、意図の誤解や情報の抜け漏れなどを防ぐことができるのです。
活用方法としては、以下のようなものがあります。
・施工現場での進行管理
・発注者や行政との合意形成
建築プロジェクトでは、携わる人数や部署も多いため、スムーズなデータ共有はプロジェクトの進行と成功に欠かせません。IFCファイルを活用することで、コスト削減や工期の短縮などが期待できます。
IFCファイルの使用方法と対応ソフト

IFCファイルは、異なるBIMソフトでも共通の形式でやり取りが可能です。正しく活用するには、ソフトごとの対応状況やデータ変換時の注意点を理解したうえで、活用ルールを定めて運用することが大切です。
IFCファイルのバージョン
BIMシステムから出力できるIFCファイルには以下のようなバージョンがあります。
|
ソフト・サービス |
バージョン |
|
GLOOBE Architect・Construction |
IFC4、IFC2×3 |
|
ARCHITREND ZERO |
IFC2×3 |
|
Autodesk Revit |
IFC4、IFC2×3、IFC2x2 |
|
Archicad |
IFC4、IFC2×3 |
|
VectorWorks |
IFC4x3、IFC4、IFC2×3 |
このようにBIMソフトによって、対応するバージョンが異なります。また、BIMソフトには海外製が多く、そもそもBIMソフトの活用は海外で進んでいるため、IFCとの連携は海外の方が盛んだと考えられます。
とはいえ、国内企業で活用する場合、海外ソフトだと取り扱い言語の面で支障をきたすかもしれません。プロジェクトを円滑に進めたい場合、日本語対応であるかもチェックしておきましょう。
ワンポイント:国内メーカーである福井コンピュータアーキテクト株式会社の「GLOOBE」は、ソフトの日本語対応は勿論の事、図面の表現や建材、施工、法規まですべて日本仕様に対応していますので安心してご利用いただけます。
IFCファイルを扱うときの注意点
IFCファイルを変換するときに、データが一部欠落したり、崩れたりすることがあります。これはソフトごとに対応している属性情報やデータの解釈が異なるためです。
たとえば、図面表現はIFCファイルに含まれないことがあります。また設定によっては建具の開閉や部材の断面情報などが反映されないケースもみられます。こうしたトラブルはプロジェクトの進行に大きな影響を与えるため、事前に対策をしておくことが大切です。
とくに国内で多く利用されている2次元CADの『Jw_cad』では、IFCとの直接的な互換性がありません。そのため、共有するときは別のファイル形式へ変換をしてから連携したり、IFC対応のソフトと併用したりといったフローを設計しなければなりません。トラブルを防ぐには、事前の出力テストやバージョンの指定など、運用のルールを決めておきましょう。
ワンポイント:国産BIMソフト「GLOOBE」はIFC形式での連携はもちろん、海外BIMソフト「Autodesk Revit」とのデータ連携にも対応しています。RVTファイルの入出力やRFAファイルの読み込みが可能で、より高精度なデータ交換を実現します。
スムーズに情報を共有し管理する方法とは
IFCファイルを使用して関係者と情報を共有する場合、どのように共有するのかルールを決めておくことが大切です。部署間で共有するデータを洗い出し、どのビューアで確認するのかフローを可視化するとルールが決めやすくなります。
また、国土交通省による建築確認手続きのデジタル化方針において、IFCファイルを活用した3Dモデルと図面情報の提出が検討されています(※1)。今後、電子申請における標準的なデータ形式としてIFCファイルがますます重視される可能性が予想されます。
制度改正にスムーズに対応するためにも、運用体制の構築とあわせてルールを決めておくことで、情報の抜け漏れや伝達ミスを防ぐことができ、スムーズにプロジェクトを進めることが可能です。
ワンポイント:木造住宅の設計を得意とする住宅BIM「ARCHITREND ZERO」もIFCファイル出力に対応していますので、木造住宅の確認申請によるIFC対応の際も安心してご利用いただけます。
※1 参考:国土交通省「BIM/CIMの進め方について」
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001867343.pdf
IFCファイルを実務で活用するなら『国産のBIMソフト』
IFCファイルは、異なるBIMソフトで建物の情報を共有し管理するための国際標準のファイル形式です。実務で活用するには、日本の建築実務に対応したBIMソフトの導入が欠かせません。
『GLOOBE』や『ARCHITREND ZERO』は、各種図面や書類・建築CGパースを一気通貫で作成するBIMソフトです。さまざまなメーカーの建材や住宅設備データと連携しているため、設計からプレゼン資料の作成までスムーズに対応可能です。国内の法改正にも迅速に対応しているため、確認申請や性能表示なども法令に沿って作成が可能です。
国土交通省が推進する建築確認のデジタル化に向けて、IFCファイル形式による提出や情報連携などへ取り組む場合、国内仕様のソフトがカギとなります。スムーズなデジタル化とプロジェクト進行のために『GLOOBE』や『ARCHITREND ZERO』の導入を検討してみませんか。以下より詳しい内容をご覧いただけます。
本記事に関連するBIM製品はこちら
●GLOOBE
https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe_s/index.html
●ARCHITREND ZERO
https://archi.fukuicompu.co.jp/products/architrendzero/index.html