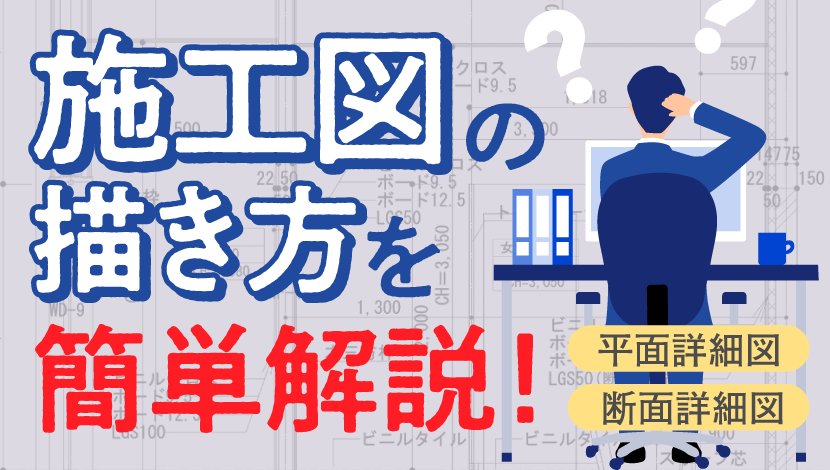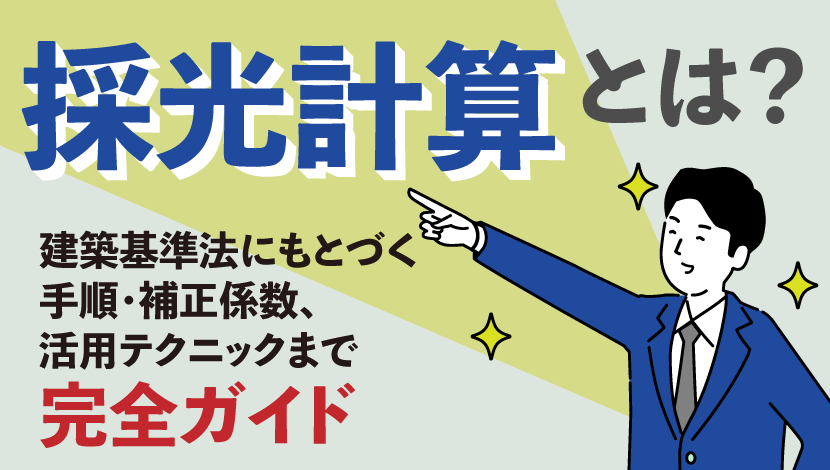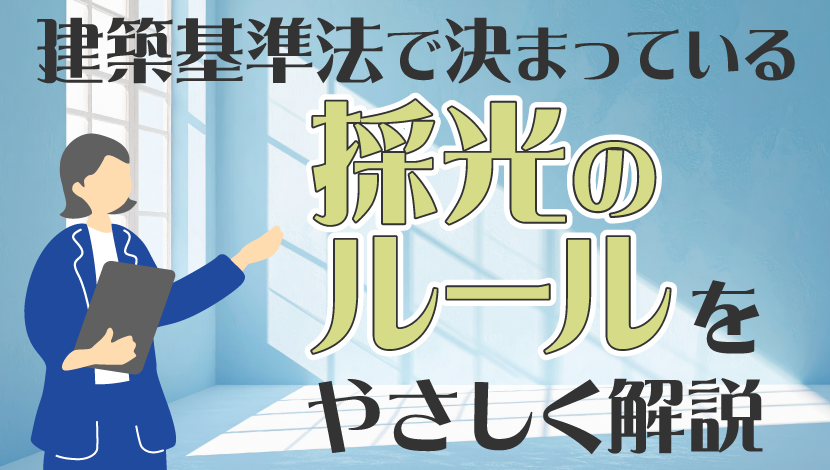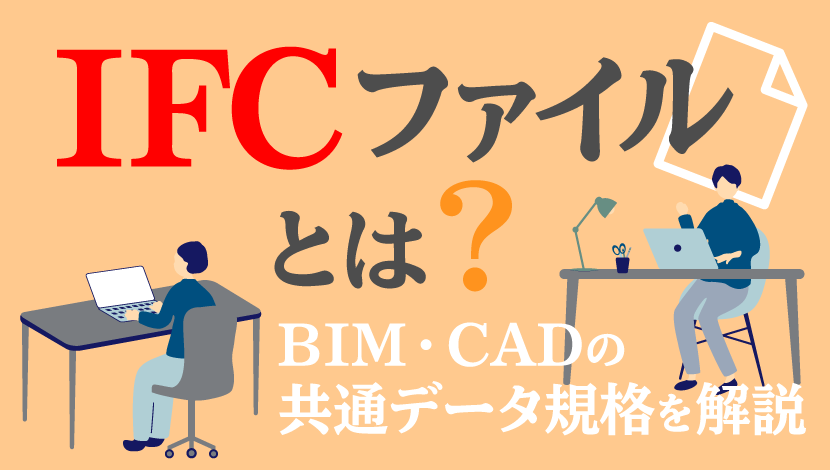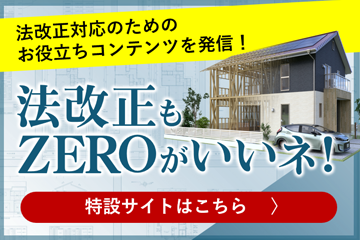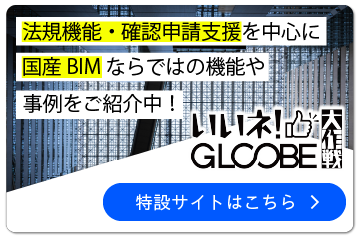施工図とはどのような図面?

そもそも施工図とは、設計図をもとに施工現場で使用するための詳細図です。建物の寸法、材料、構造、仕上げなど工事に必要な情報が正確に表現されます。
設計図が意図を伝える図面だとすれば、施工図はそれをどう形にするかを示す図面です。たとえば、設計図では省略されがちな配管や納まりのディテールも、施工図では正確に描かれ、現場作業の迷いやミスを防ぎます。
まずは施工図の役割を正しく理解

施工図を正しく描くためには、まずその役割と目的を理解しておく必要があります。施工図の果たす主な役割は以下の3つです。
過不足のない情報を工事作業者・職人へ伝える
現場では、限られた時間と人員のなかで、正確かつ効率的な作業が求められます。そのため、施工図には職人が迷わず作業に着手できるよう、寸法や納まり、材料の種類や位置関係などが過不足なく記されていなければなりません。
情報共有の円滑化
施工現場では、建築、電気、設備など複数の業種が並行して作業を進めることが一般的です。そうしたなかで、各業種間の連携をスムーズに行うには、共通認識のもとで情報を共有できる施工図が欠かせません。
施工ミスや各工事の干渉の防止
施工図は、建物の各部位がどのように構成され、どの順序で作業すべきかを明確に示します。たとえば、設備配管が梁や鉄筋に干渉してしまうと、手直しが発生し、工期やコストに影響が出る可能性があります。
こうした工事同士の干渉リスクを事前に排除するために、施工図には断面図や詳細図を含め、3次元的な視点での情報整理が必要です。
施工図の種類とそれぞれの違い

施工図とひとくちに言っても、その種類は多岐にわたります。各図面はそれぞれ異なる目的と役割を担っており、用途に応じて適切な形式と内容で作成されなければなりません。
ここでは、現場でよく使われる主要な施工図の種類とそれぞれの特徴について解説します。
平面詳細図
建物を上から見た状態を表した図面です。各部屋の間取り、壁の配置、出入口の位置、設備機器の配置、仕上げ材料などが描かれています。施工図としての平面図では、設計図よりもさらに具体的な寸法や納まりが記載され、作業手順を想定した情報が追記されます。
断面詳細図
建物を垂直に切断した断面の構造や仕上げの情報を示す図面です。天井高さや床厚、梁や柱の位置関係、階層ごとの構造納まりなどが視覚的に理解できます。とくに、上下階をまたぐ構造要素や、仕上げ材の取り合いが複雑な部分で使用されます。
躯体図
構造体である柱、梁、壁などの寸法や位置、配筋などが詳細に描かれた図面です。構造設計の成果を反映しつつ、実際の施工方法に即して編集されるため、施工中の精度確保に直結します。RC造やS造の現場では必須の図面です。
天井伏図
天井を下から見上げた図面です。照明や点検口、空調設備の位置、天井仕上げの種類などが記載されます。
配管図
給排水や空調、ガスなどの配管経路を示す図面です。配管の勾配やサイズ、支持金具の位置なども含めて記載され、他の構造や設備との干渉を避けるために重要な役割を担います。
割付図
仕上げ材(タイル、フローリング、パネルなど)の配置を示す図面です。素材ごとの寸法や目地の位置、端部処理などを確認でき、意匠性と施工性の両面から重要です。仕上がりの印象に直結するため、施主確認や現場指示で活用されます。
プロット図
建物全体の配置を示す図面で、敷地に対する建物の位置関係、周辺環境との境界、外構との取り合いなどが記されています。敷地内の高さ関係や通路計画など、初期の段階での調整事項にも関与します。
外構図
建物外周の舗装、植栽、フェンス、水道や排水の外構設備などを描いた図面です。建物本体だけでなく、敷地全体を含めた計画が施工レベルで整理されており、官公庁への提出や近隣対策にも利用されます。
施工図「平面詳細図」の書き方

ここでは、施工図の基礎である平面詳細図の書き方を紹介します。
1.壁と柱の中心線の設定
中心線とは、柱や壁の芯を示す基準線で、壁厚や柱配置の起点となります。ずれが生じると、寸法や仕上げ位置にも影響が及ぶため、正確な設定が不可欠です。
【作成ポイント】
- 設計図を基に、建物全体に通り芯(グリッド)を設定します。 通り芯は図面の四方すべてに記載し、他の図面との照合を容易に行えるようにしましょう。
- 通り芯の交点に柱や壁を配置し、中心が正しく一致しているか確認します。
- 柱位置は各階で整合しているか、構造図と綿密に照合しておく必要があります。
- 外寸基準で描くか、芯寸法で統一するかを事前に決定します。特にリノベーションや敷地境界線からの離れなど、法的要件や周辺状況によっては外寸基準での整合性が重要になります。
2.壁と柱の線の下書き
中心線の設定後は、壁と柱の輪郭線を下書きします。中心線を基準に、壁厚や柱寸法を反映した形状をラフに描き、後の清書に備えます。
【作成ポイント】
- 壁の厚さは材料に応じて設定し、厚みは中心線をはさんで両側に展開します。
- 柱は通り芯の交点に正確に配置し、構造図と寸法・形状の整合を確認します。
- 修正しやすいよう、線種やレイヤーを適切に使い分けましょう。
- 未確定部分は未確定であることを明確に示し、確認待ちである旨を明記します。
3.壁と柱の線の清書
ここでは、図面として提出できる品質を目指し、線の種類やレイヤー設定を整えて、視認性と正確性の両立を図ります。
【作成ポイント】
- 柱や構造壁は太線(例:0.3mm)、間仕切り壁は細線(例:0.1mm)を使い、構造体と非構造体を明確に描き分けます。
- 通り芯や寸法補助線は破線・点線で表現し、レイヤーごとに色分けや表示の制御を設定します。
- 壁端部や柱との取り合い、仕上げ材の厚みによる内寸の変化など、細部の納まりを正確に描写します。
- 各階で壁位置が通り芯に対してずれていないかを比較し、構造全体の一貫性を確認します。 特にRC造などでは、構造壁の上下階でのずれは構造的な問題に直結するため、徹底した確認が必要です。
4.開口部の情報の追記
次にドア・窓・シャッターなどの開口部の位置と寸法を追記します。
【作成ポイント】
- 開口部には「D-1」「W-2」などの記号を割り当て、詳細な寸法や仕様は建具表や仕様書で管理します。
- 配置は壁芯や通り芯からの寸法で指定し、サッシやドア枠の納まり(壁厚の中心、壁の面合わせなど)も考慮した上で正確に描きます。
- 補強筋やスリーブとの干渉が起きないよう、構造図・設備図との整合性を必ず確認します。
- 防火戸や防音サッシなどの特殊建具は、法規対応や性能表示(認定番号、耐火時間など)の記載も忘れずに行います。
5.設備器具・床仕上げの書き込み
施工図では、設備器具と床仕上げの情報を正確に反映させることが重要です。これらは建築・設備・内装の各工程にまたがるため、調整の精度が施工全体に影響します。
【作成ポイント】
- 洗面台・便器・キッチン・エアコンなどの位置は、製品寸法や給排水・排気経路、配管位置、コンセント位置を基に記載します。特に水回り設備は、壁からの距離や給排水芯、上下階との整合が施工精度に直結するため、設備図との綿密なすり合わせが必要です。
- 床仕上げは、使用する材料(フローリング・タイルなど)や段差、仕上げの切り替え位置を示します。
- 配管・配線スペースだけでなく、設備の経路や必要な躯体開口なども考慮し、設備との調整内容を図面に具体的に反映させます。
6.詳細(基本線・方位・部屋名・室内線など)の追記
平面詳細図の仕上げとして、通り芯、方位、部屋名、有効寸法などの補足情報を追記します。
【作成ポイント】
- 通り芯記号(例:「A〜E」「1〜5」)は図面の四方すべてに記載し、他図面との整合性を保ちます。
- 方位記号は、採光や設備配置に関わるため、北方向を明示することにより空間の向きを明確にします。
- 部屋名は空間の用途を明示し、施工内容の誤認を防ぎます。図面と現場の認識ずれを防ぐために重要です。
- 有効寸法(内装仕上げ後の最終的な空間寸法)もあわせて記載します。 これは家具配置のためというよりは、施工後の実際の空間の広さを明確にするために重要です。
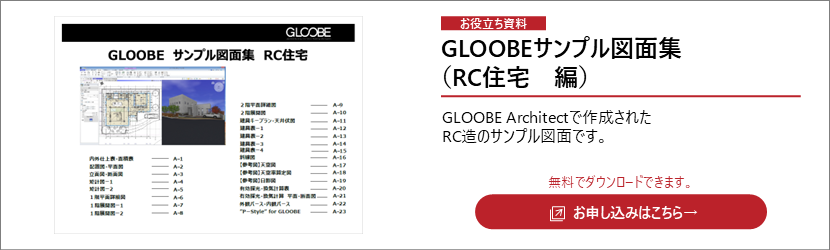
施工図「断面詳細図」の書き方

ここでは、断面詳細図の書き方を見ていきましょう。
1.中心線の設定
まずは中心線を設定します。
【作成ポイント】
- 設計図を基に、柱や梁の芯に中心線を通し、構造要素の重心を明確にします。
- GL(地盤面)を起点とし、FL(フロアライン)や天井・屋根の高さを±0基準で統一して記載します。これにより、高さ関係が図面上で一目で把握できる構成になります。
- 階段やエレベーターなどの垂直動線についても、中心線を基準に寸法の精度を確保します。
2.梁や柱の記載
中心線を設定した後は、柱や梁といった主要構造部材を図面に記載します。
【作成ポイント】
- 柱は、階ごとの位置・断面寸法・構造種別を記載し、平面図と必ず整合を取ります。 階をまたぐ場合は、柱サイズの変化や納まりに注意が必要です。
- 梁はスラブ下や柱間に配置し、位置・断面形状・梁せいを明記します。天井高や設備配管との干渉を避けるため、正確に寸法します。
また、梁と柱の納まり(梁勝ち・柱勝ち)は断面補足図などで補足し、必要に応じて構造設計者と調整を行います。また、スリーブや補強筋など施工上の注意点も記載しておくと、現場での判断精度が向上します。
3.壁の線の記入
構造体の記載が完了したら、外壁・内壁・間仕切り壁を断面図に描き入れます。
【作成ポイント】
- RC造の外壁は200mm程度を太線で、軽量間仕切り壁は60〜100mm程度を細線で描き分け、構造的な役割の違いを視覚的に明確にします。
- GLからの外壁立ち上がりやパラペットの高さなど、外部との取り合い寸法も記載します。
- 構造体・断熱材・仕上げ材の層構成は、注釈や断面記号を用いて明示し、内装範囲と構造範囲を明確にします。
4.床・天井の情報の記入
床と天井の情報は、断面詳細図の中でも構造・仕上げ・設備が交差する重要な領域です。正確な記載によって、納まりの整合性が確保され、施工ミスや干渉の防止につながります。
【作成ポイント】
- スラブ厚、下地、仕上げ材を含めた床の総厚を記載し、階高・天井高との整合を図ります。
- 吊り天井の懐寸法(天井裏の空間寸法)、天井下地・仕上げ構成を明示し、空調や電気配線、防災設備など、あらゆる設備との干渉を避けるよう調整内容を反映します。
- 点検口やダウンライトの納まりも図示し、設備工事との調整を円滑にします。
- 床下や天井裏に配管・配線を通す場合は、それに必要なスペースや勾配の寸法も断面上で反映します。
- 吹き抜けや勾配天井などの特殊納まりについても、形状・寸法を正確に描きます。
5.仕上げ材の書き込み
断面詳細図では、床・壁・天井の仕上げ材を記載することで、施工品質と意匠性を担保し、現場での判断ミスを防げます。
【作成ポイント】
- 床仕上げはフローリング・タイル・長尺シートなどを用途別に選定し、スラブ上に厚みと素材名を注釈で記載します。
- 壁は構造体に下地材・仕上げ材(クロス・塗装等)を重ねて描き、防火・遮音・耐水といった機能要件がある場合はその仕様を補足します。
- 天井仕上げは吸音板・化粧ボードなどの構成を示し、有効天井高・照明器具・点検口の納まりも含めて記載します。
- 外壁は断熱・通気・防水・仕上げを層構成で描写します。特に防水層やシーリング材、水切り材は建物の耐久性や防水性能に直結するため、詳細に表現しましょう。
6.見えがかり線での仕上げ
仕上げ部分の見えがかり線を明確に示すことで、現場での判断のばらつきや施工ミスを防ぎます。天井と壁の取り合い、床と巾木、開口部まわりなど、視線が集まりやすい箇所は特に重要です。
【作成ポイント】
- 見えがかり線は、通常の断面線よりも太線(または異なる線種)で描き分け、隠れた構造体と区別することで、最終的な仕上げの状態や施工範囲を明確にします。
- 階段や吹き抜け、梁と天井の接点なども見えがかり線で完成形を示し、干渉リスクや施工誤差を防ぎます。
- 目地や折り上げ天井などのデザイン要素も図示し、設計意図を正確に共有します。
7.詳細(部屋名・寸法など)の追記
断面詳細図の仕上げとして、部屋名と寸法を追記します。これは、どの空間に、どの寸法で施工するかを明確に伝えるための重要な工程です。
【作成ポイント】
- 断面図にも部屋名を記載し、平面図と整合を図ります。用途を明示することで誤施工を防止します。
- 階高、天井高、梁せい、スラブ厚などの主要な寸法を明示し、有効天井高やパラペット高さも図示します。
- 通り芯からの高さや壁厚など、関連する寸法を詳細に記載し、寸法の累積誤差を防止します。
- 床下・天井裏の有効寸法や設備スペースも併せて記載し、設備計画や施工判断を支援できる実務的な図面とします。
施工図を作成する際のポイント

ここでは、施工図作成における重要な実務ポイントを2つ紹介します。
スケールの確認
施工図の基本は、使用するスケール(縮尺)を明確に定めることです。スケールは寸法の意味を正しく伝えるために不可欠で、図面の読みやすさと精度を左右します。
一般に、平面・断面詳細図では1/50、部分詳細では1/10〜1/5、ゾーニングなど全体把握には1/100〜1/200が用いられます。
重要なのは、用途に応じて適切な縮尺を選び、図面上に明記することです。スケールの混在は誤読・施工ミスにつながるため注意が必要です。
また、印刷時の縮尺変化を想定し、スケールバーや寸法線を併記すると、確認精度の維持に効果的です。
使用するツールの選定・準備
施工図の多くは建築CADで作成されており、整合性の確保や修正対応、データ共有など業務効率が大幅に向上しています。
ただし、ツールの導入だけでは不十分で、操作担当者の理解や、レイヤー管理・線種ルール・テンプレートの整備が不可欠です。
社内外との共有を見据え、PDF・JWW・DWG・IFCなど多様な形式での出力対応も必要でしょう。

社内教育や研修で施工図の書き方を教えるときのポイント

施工図の教育では、ツールの使い方だけでなく、図面の役割や目的を理解してもらうことが大切です。
ここまで見てきたように、施工図は設計図の清書ではなく、設計の意図を現場に伝えるための翻訳図であり、実際の施工を支える情報図です。
設計図との違いも明確にし、施工図には寸法や納まり、施工順序など、具体的で現場視点の情報が含まれることを知ってもらいましょう。図面は現場との対話の手段でもある、という意識を持ってもらうことが重要です。
作図の手順についても、通り芯の確認から平面・断面図の記載、図面間の整合確認、仕上げや寸法などの補足といった流れを通じて、背景を含めて理解を深めてもらいます。
また、実際の施工写真や完成建物と図面を見比べることで、図面と現場のつながりを実感してもらうサポートも効果的です。
【まとめ】建築・施工の現場で役立つ施工図を正しい書き方でまとめよう
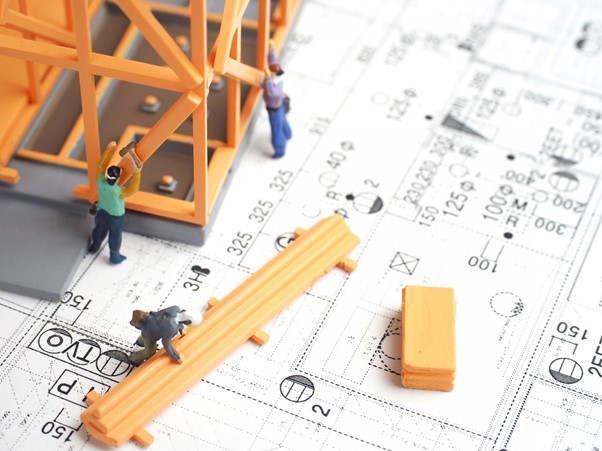
現場で使える施工図とは、情報の過不足がなく、誰が見ても迷わず施工できる図面です。
こうした施工図を効率よく、かつ高品質に作成するためには、CADやBIMのような専用ツールの導入も有効です。
BIMモデルとの連携により、平面・断面・詳細図の整合がとれた図面を効率よく作成でき、手戻りやミスの削減にもつながります。
なお、福井コンピュータアーキテクトでは、BIMの無料体験版や各種資料、導入相談、セミナーなどを提供しています。
特別な設定なしですぐに始められる施工BIMソフト「GLOOBE Construction(グローブコンストラクション)」をはじめ、初心者の方でも安心して導入いただけるソフトウェアが揃っていますので、 ぜひ以下のリンクをご確認ください。
無料体験版のお申込み:https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe_c/download_c.html
見積りや導入のご相談:https://archi.fukuicompu.co.jp/form/consult.php
イベントやセミナー情報:https://archi.fukuicompu.co.jp/event/index.php?prm=bui