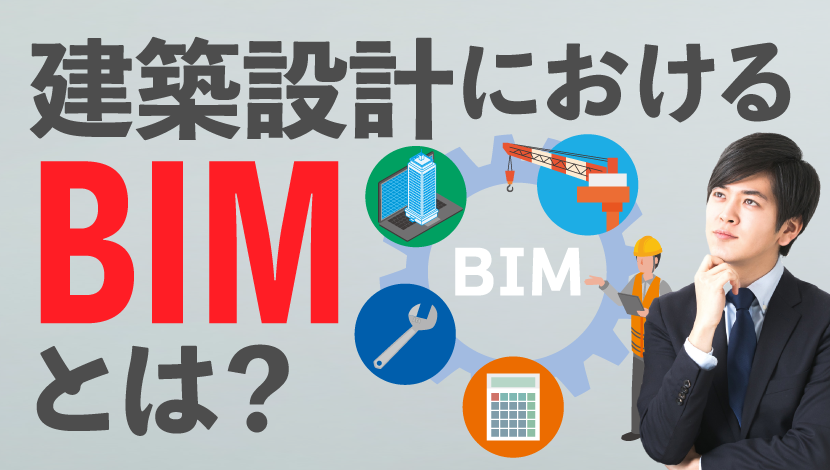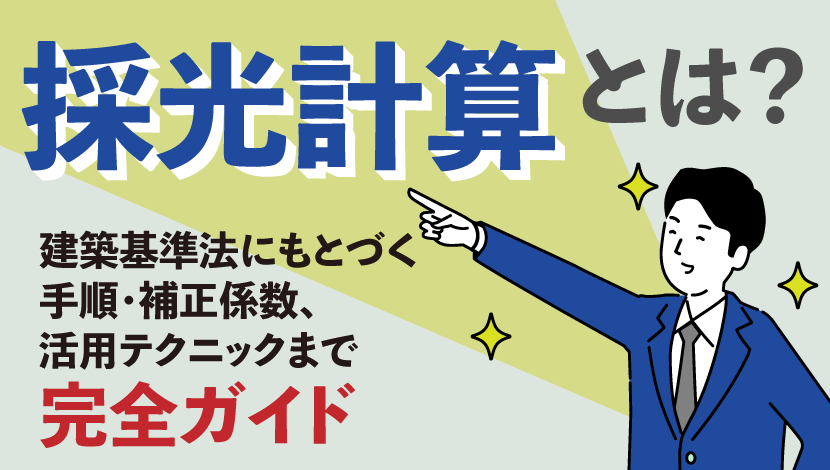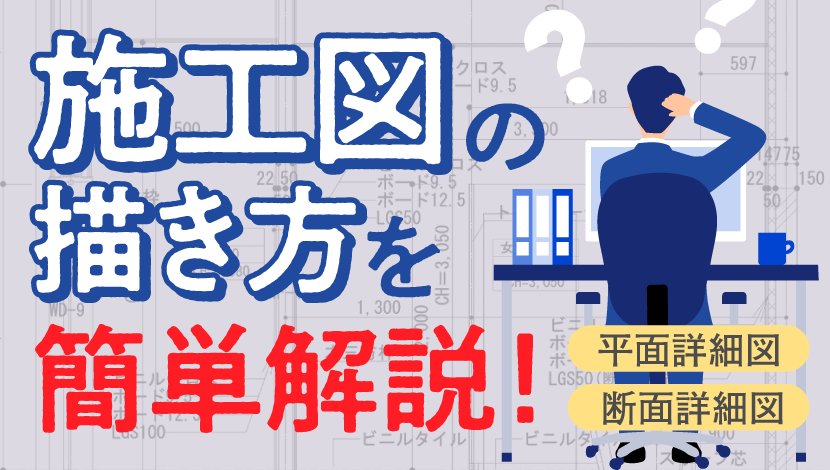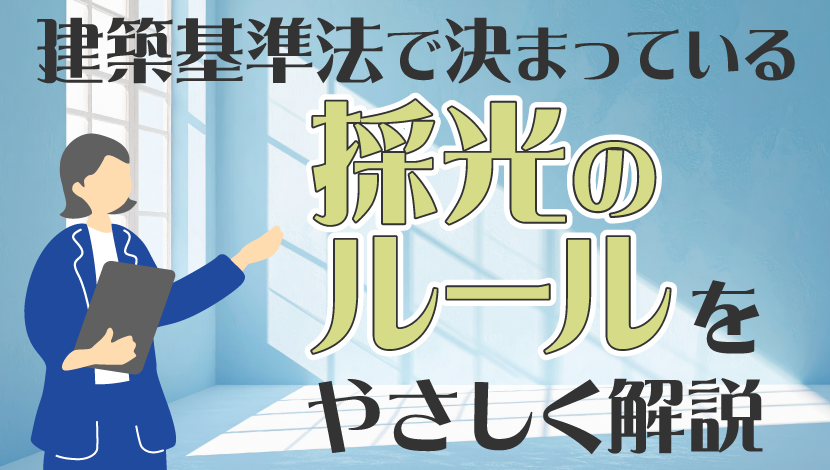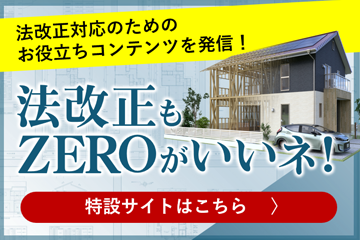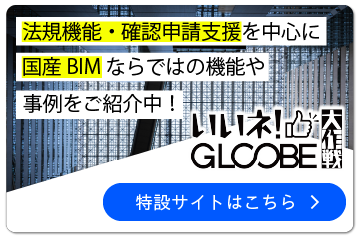BIMとは

BIM(ビム)とは、「Building Information Modeling」の略語で日本語では「建物を、情報で、形成する」という意味があります。具体的にはコンピュータ上に作成する、現実の建物と同じ3次元デジタルモデル、およびそれを利用して進めるプロセスやプロジェクトそのものを指します。
BIMの特徴や基本情報について解説します。
BIM専用のソフトウェア・アプリケーションをもちいて作成する画期的な建築3次元モデル
BIMモデルは、建築設計用(BIM専用)のソフトウェアやアプリケーション(BIMツール)を使用して作成されます。 建設する建物の 3Dモデルをデザインとして作成するだけでなく、3Dモデルをベースとして設計や施工、その後の管理やメンテナンスまで含めすべての工程で共通のデータを活用できるという点が 、BIMの持つ画期的な特徴です。建築物の完成イメージや、さまざまな変更による構造や印象の変化などを都度、 視覚的に理解しやすいというメリットがあります。
建物の意匠表現だけでなく、設備設計情報やコスト・仕上げなど付随情報がすべてBIMに含まれる
BIMツールで作成されたBIMモデルは、オブジェクトの集合体です。各オブジェクトには、以下のような様々な情報を付与できます 。
・建材部材・パーツの情報(幅や奥行き、高さ、素材、工程、組み立て時間等)
・構造体の仕様や情報
・設備機器の情報(品番、メーカー、価格等)
建物の意匠表現をするだけでなく、設計変更後のシミュレーションや、資材管理、メンテナンスや修繕時期の管理対応、概算コストの計算などの多くの業務にも活用できます。
単なる3次元モデルではなく、設計・施工から維持管理まで建築ライフサイクル全体で活用できる統合データベースとなる
BIMモデルでは3次元モデルだけでなく 、付帯されたあらゆる詳細情報を活用することで設計、施工、維持管理などにも使用可能です。建築プロセスにおける建築情報の基盤であり、建築ライフサイクル全体で活用できる、統合データベースとしての役割も果たします。
BIMと3D CADやCGパース、CIMとの違い

建築分野では、BIMのほかにも3D CADやCG パース、CIMなどが設計の際に用いられています。これらの 設計技術方法の特徴と、BIMとの違いについて順に解説します。
3D CADとBIMの違い
3D CADとは「3D Computer Aided Design」の略語で、3次元(立体)の設計支援を行う技術・および ソフトウェアです。2次元(平面)の設計を行う2D CADに対して、3D CADは設計物の形状を直感的に理解しやすく、特に複雑な建築物の表現に向いています 。
BIMが3Dモデルと建築のデータベースそのものを構築する技術であるのに対して、3D CADはあくまで設計図面の作成を主目的 としています。ただし、オートデスク社の「Autodesk Revit」のように、3D CADで作成したモデルをBIMモデルとして活用できるBIMツールも誕生しています。
CGパースとBIMの違い
CGパースとは、英語で「Computer Graphic Perspective」と表現し、コンピューターグラフィックスを使用し建築物の外装や内装を三次元化し、立体的に表現した画像のことです 。おもに建物の外観イメージや使用イメージの確認に使われています。
CGパースは、BIMや3D CADで作成した3次元モデルを元に作成されます。そのため、3次元モデルとCGパースが別々に存在している状態です。3Dモデル側に変更や修正があっても、CGパースへは別途対応が必要となり、リアルタイムでは反映されません。
ワンポイント:GLOOBEやARCHITREND ZEROはリアルタイムでモデルデータと連携しているので、CGパースとの整合を保つことができます。
CIMとBIMの違い
CIM(シム)とはConstruction Information Modelingの略称で、BIMと同じく 3Dモデルを使った建設情報のモデリング技術です。BIMが住宅やビルのような建物などの建築物を対象としているのに対して、CIMは橋やダムなどの土木やインフラ分野の施工物を対象としている点に違い があります。
日本ではBIMとCIMの定義を対象分野で明確に分けている一方で、海外の一部では、日本でいうところのCIMをあくまでBIMの中の一種と認識しているケースもみられます。
建築設計に建築BIMを導入するメリット

BIMは建築設計分野の各企業への普及が、今後も期待されている技術です 。BIMを導入することで得られる具体的なメリットを解説します。
設計・施工時の修正手間を大幅に軽減できる
BIMを導入することによって、設計や施工における、大小さまざまな修正の手間を大幅に軽減する事ができます。 BIMは3Dモデルと建築物に関する情報データベースの 両方の役割を持っており、他者との共有も簡単に行えるため 、意匠や構造、設備の設計などあらゆる工程で関係者との コミュニケーションもスムーズに行えます。
各関係者のやり取りの過程で生じた 修正点も、3Dモデルの設計情報へ即、連動・反映することが容易なため、 従来の手法のように個別に設計を描き直す必要もありません。配筋本数の計算や干渉回避なども自動算出できるため、施工上でのミスの防止にもつながる でしょう。
建築の初期提案から完成までの⼀貫性を確保できる
BIMでは、BIMモデルを通じて視覚的な合意を得てから設計図書の作成に⼊ります。初期に提案したイメージそのままのかたちで設計・施工へと進めていけるため、 提案と完成物の差異を最小限にできるのがメリットです。初期段階で視覚的な確認を随時行っておくことで、設計段階での内容変更や手戻りが少なくなり、時間や費用面でのロスも発生しにくくなるでしょう。
ワンポイント:GLOOBEでは、BIMモデルデータから図面を切り出して自動生成するだけでなく、図面生成後に行ったBIMモデルへの変更も瞬時に図面へ連動しますので、更に設計変更での手戻りやロスを最小限に押さえることが可能となります。
クライアントとの合意形成に役立つ
建築BIMは従来の手法と異なり、設計初期段階から2次元データではなく、より詳細な3次元のデータを取り扱います。クライアントに設計を提示する場合でも、3Dモデルを通じて建物の外観、内装、空間、設備などをより具体的にイメージできるようになるでしょう。
2次元データでは把握できない詳細な部分も視覚的に確認できるため、クライアントの思い違いや勘違い、認識のズレなどの防止や低減にも高い効果を発揮します。
クライアントからの要望があった場合も、3Dモデルに要望の内容を反映してすぐに確認できます。工程が進んでからの 大幅な設計変更を避けられる ため、工期やコストの削減にもつながるでしょう。
国土交通省は公共事業のほぼすべてにおいてBIMやCIMを義務化

国土交通省は2020年3月に「BIM/CIM活用工事における監督・検査マニュアル」や「発注者におけるBIM/CIM実施要領」を作成、さらに、2023年までに公共事業(小規模工事以外の全て)について、「BIM/CIM」を原則適用する旨を決定しました 。以前はBIM/CIMの適用は2025年までを目標としていましたが、「BIM/CIMを浸透させていく」という強い意思から、運用開始が当初よりも2年前倒しとなっています。
2026年春までには、建築確認におけるBIM図面審査も開始される予定です。BIM図面審査の申請時には 従来の紙の図面に代わり、BIMデータの作成等に関する入出力基準に基づいたBIMソフトウェアで作成した以下のデータを提出することになります。
・申請図書(PDF)
・設計者チェックリスト
・BIMモデル(IFC)
BIMによる建築確認の図面審査を採用することで、従来の方法と比較し申請者や審査担当者に 以下のメリットが得られます。
・BIMソフトウェアを使用することで、整合性の高い申請図書を簡単に作成できる
・窓口に出向かず自社内からオンラインで 申請・指摘事項の対応ができ、申請作業の効率化につながる
・審査が効率化することで、審査期間の短縮が期待できる
・設計内容をスムーズに把握でき、整合性確認の一部も省略できるので、審査作業の効率化が図れる
・確認申請クラウド(CDE:Common Data Environment)を使用すれば複数人による並行作業、遠隔拠点やテレワークでの作業も可能となる
参考:国土交通省「BIM/CIMポータルサイト」
https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html
参考:国土交通省「BIM/CIM活用工事における監督・検査マニュアル」
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001334924.pdf
参考:国土交通省「発注者におけるBIM/CIM実施要領」
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001395761.pdf
BIMの具体的な導入ステップ

建築確認におけるBIM図面審査や将来的なBIM導入の義務化が決定しているため、これからBIMの導入準備を進めようとしているものの「どのように導入を始めるべきか分からない」と悩む人も多いかもしれません。
BIMの具体的な導入方法を、ステップ順で解説します。
BIMについての基本理解をしておく
BIM導入でまず始めなければいけないことが、BIMについて知ることです。以下のような媒体や方法で、BIMについての基本情報や概要、導入することで得られるメリットなどを理解しておきましょう。
・書籍
・SNSやホームページなどWeb上の情報
・BIMソリューションや支援サービス提供ベンダーの配布資料
・製品デモや体験版ソフト
・導入事例の動画
・BIM未経験者向けセミナーやイベント
・BIM導入済み企業からの情報収集や意見交換
・BIM活用企業のコミュニティ参加
BIMの活用目的を明確化しておく
BIMの基本情報や導入メリットなどを知った後は、自社でのBIMの活用目的を明確にしておきます。実際に導入するプロジェクトや、運用体制によって導入すべきBIMソフトやツールが異なるためです。
BIMの活用目的を明確化する際にはまず、既存顧客・クライアント側のニーズと自社の課題と照らし合わせましょう。ニーズの充足、課題の解決のためにBIMを活用するという具体的なイメージを持てば、おのずとBIMに必要な機能や運用体制が把握できます。
導入するBIMソフトウェアを選定する
BIMを導入する目的を明確にしたら、続いて BIMソフトウェアやツールの選定に入ります。ベンダー各社のリリースしている体験版やデモを活用し、実操作上での問題はないか、自社の運用面での相性は良いかをチェックし、ソフトウェアやツールの候補を絞ります。
ベースとなるBIMソフトウェアだけでなく、データ連携に用いるソフトウェアなども合わせて選定を行います。ある程度候補となるソフトウェアが出てきたら、社内の既存システムやソフトウェア、データなどとの 互換性、費用、サポート状況などを確認し、具体的なソフトウェア選定につなげます。
環境を整備し、仮ワークフローを作成する
BIMソフトウェアを選定したら、まずは試行を繰り返して以下のような必要な標準データの整備を行いましょう。
・プロジェクト開始に必要となる基本設定をまとめたテンプレート
・情報部品のライブラリ
・モデリングのルールブック等
最初はベンダー側で提供しているテンプレートを活用したり、スターターパックの導入を検討したりといった方法がおすすめです。標準データをある程度整備できたら、社内で目的に対してどのようにBIM導入を実施 するか、運用するかをまとめた標準的なワークフローを仮作成しておきます。
BIMを導入する
BIM導入時、標準データと仮のワークフローをベースにして、組織の規模に合わせた社内の教育を実施します。標準データと仮のワークフローを、実プロジェクトへ反映していきましょう。
BIMを実プロジェクトへ導入できた後は 、仮ワークフローやモデリングルールの段階では気付かなかった不備や改善点、既存の標準データの不足などが見つかることもあるでしょう。
設計部門からのフィードバックを取り入れて、ワークフローやモデリングルール、標準データの見直しを進め、BIM運用の環境整備を進めましょう。
BIM推進に向けた外部サポートを活用する
BIMは操作上はCADと似た部分があるものの「モデリングがうまくいかない」「モデルに付帯する情報の整備ができない」「現場になかなか浸透しない」といった課題が出てくる ことも多いかもしれません。
その場合は、以下のようなBIMに関する外部サポートの 利用を検討しましょう。
・BIM関連コミュニティ
・セミナー参加
・BIMコンサルタント、支援ソリューションなどの外部委託
BIMの作業効率向上を図る
BIMの導入初期段階をクリアし、実プロジェクトへの運用が開始されたら、以下のようなBIMの作業効率向上のための取り組みを行いましょう。
・社内でのBIM人材育成
・リスキリング
・既存2DデータをBIMに取り込み集約
・XRツールとの連携利用
・共通データ環境の整備
・建築確認申請への展開
設計分野でのBIMの導入が軌道に乗り始めた段階で、 各フェーズ(設計、施工、維持管理)でのデータ連携につなげBIM 3Dモデルを最大限活用できる体制を構築します。クラウド環境や協働プラットフォームを構築し、BIMを通じたコミュニケーションや協働作業が実現できる環境を整備しましょう。
BIMの導入や運用でお悩みの際には、外部の導入支援サービスの検討もおすすめです。福井コンピュータ アーキテクト株式会社では、「BIM建築設計支援システムGLOOBE Architect 体験版」の公開をはじめ、BIMソフトウェアの操作・活用支援セミナーの開催や各種解説動画を公開しています。
BIMソフトのデモ導入依頼やお見積り、ご相談もいつでもお気軽にお寄せください。
無料体験版のお申込み:https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/download.html
見積もりや導入のご相談:https://archi.fukuicompu.co.jp/form/consult.php
イベントやセミナー情報:https://archi.fukuicompu.co.jp/event/index.php?prm=bui
【まとめ】 建築業界の業務効率化とDX推進には、BIMの導入・活用が不可欠
本記事ではBIMとは何か? といった基本的知識に加えて、3D CADなど従来のモデリング手法との違い、導入するメリット、導入ステップなどについてまとめて解説しました。
建築確認申請のBIM図面審査も2025年より開始されます。
自社でBIMを導入する目的を明確にし、適切なソフトウェアやツールを選定し、BIMによる建築プロセス構築につなげましょう。